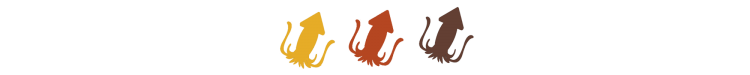◎下宿とシェアハウスの「感覚的な」違い
◆似たような話を前にもしたような。。
「シェアハウスと下宿の違いを考えてみよう。」にて似たような話をしました。
その中で一般的な違いとして、
▶共通点
中長期の居住者のための施設。運営母体(管理者)がある。居室(寝るところ)以外のキッチン、トイレ、浴室などは共同設備を利用する。
▶相違点
●シェアハウス
デザイン性やコンセプトを付加価値にしている。その分、家賃はアパートやマンションに比べても同額か若干安い程度。管理者は常時施設内に居らず、トラブルには来訪して対応。
●下宿
管理者が常駐、または近隣に住んで対応する。トイレ、風呂(銭湯の場合も)が共同で台所が個室内にある場合や、台所も共用設備で食事の提供をしているところもある。普通の戸建ての「部屋貸し」も下宿と呼んだりする。
主観的な違いとして、
▶共通点
運営母体(管理者)がある。居室(寝るところ)以外のキッチン、トイレ、浴室などは共同設備を利用する。住民同士で交流がある。
▶相違点
●シェアハウス
デザイン性に力を入れていて、イベントも積極的に主催、または開催を推奨する仕組みがある。その運営費用がかかるため、家賃は近隣アパートと比べて同額か若干安い程度。場合によっては高いことすらある。管理者は常時施設内に居らず、トラブルには来訪やオンラインで対応。
中長期の入居が多く3ヶ月程度で出る人も。出入りが多い分、新しいメンバーで過ごせて新鮮。
●下宿
管理者が常駐、または近隣に住む。シェアハウスほどシステム化されていないためよく言えば人間味がある。悪く言えば効率が悪い(商売が下手、または大家さんは他に仕事をしていて副業としてやっている)。平穏な日常を大事にしているため家賃的にもリーズナブルな設定をしている。そのため設備的にはあまり付加価値がついていない。ありのままの設備が気に入るか否かで好みが分かれる。
多くの人と出会う、多くの人と交流するというシェアハウスより「日常」「ふつうの暮らし」に重点を置いているため、長期の人が多い。
というお話をしました。
◆他にも。。
他にも下宿やシェアハウスについて↓↓↓↓↓のようなお話もしています。
▶(一般的な)シェアハウスと一人暮らしのメリット・デメリット
が!
おぼろげな話は共通していますが、書き方を変えると伝わりかたも変わるかと思いますので、今回は「感覚的な」違いとして下宿とシェアハウスの違いを見ていこうと思います。
◎貸しルームにおける入居実態等に関する調査

◆シェアハウス等における契約実態等に関する調査
国土交通省が平成26年(2014年)に公表した「シェアハウス等における契約実態等に関する調査」をもとに、シェアハウスに住む人たちの傾向を見ていきたいと思います。
その傾向を見れば下宿とシェアハウスの共通点や相違点が分かるんじゃないかと思っています。
◆シェアハウスの入居目的
シェアハウスにおける入居目的ですが、
「家賃が安いから」「立地が良いから」「初期費用が安いから」や「不動産屋での手続きが不要だから」「家賃債務保証会社が不要だから」「連帯保証人が不要だから」といった一般的な不動産と比べて手続きが簡略化されていたり、費用が安く抑えられて引っ越しや移住が気軽にできることがシェアハウスに入居する目的として大きくなっています。
そして、案外少ないのが「イベントなど楽しそうだったから」「コンセプトが気に入ったから」「集まって暮らす安心感がある」「共用スペースが充実しているから」「他の居住者とコミュニケーションがとれるから」あたりです。
入居する理由として挙がってはいる項目ですが、費用面、手続き面と比べると弱い感じです。
費用面は共用スペースがあるのがシェアハウスですから、費用が抑えられるのは当然としていいのですが、連帯保証人などの手続きを簡便化させているのは「間口を広くして入居者をたくさん募れる」「諸事情がある人も住むところを得られる」という面でいいと思うのですが、少なからず入居後の住民間のトラブルの原因にもなりそうな気がしていて、ちょっと疑問が残るところです。
◆「ツナギ」の要素もあるシェアハウス
入居があれば退去もあります。
シェアハウスを退去したときの理由としては「職場の異動・結婚等、自身の状況の変化により転居せざるを得なかったから」「当初から短期的に居住するつもりだったから」「もっと良い物件を見つけたから」あたりが多い回答になりました。
気になるのが「当初から短期的に居住するつもりだったから」です。
この回答から、一時的、避難的、「仕方なく」な側面が見え、積極的にシェアハウスを選択していないネガティブな要素が見え隠れします。
また、「想像していた共同生活と違っていたから」「入居者のマナーが悪いから」「入居者間のトラブルがあったから」などの回答もあり、共同生活ならではの退去理由もありますが、これらは入居時のルールなどの説明不足や間口を広げてどんな人でも家賃さえ払えば入居させてしまうというシェアハウスがあることから出てくるもので、少なからずそういったシェアハウスがあることで、シェアハウス全体のイメージにとってマイナスに働いているように思えます。
◎感覚的に考える「下宿」の姿とシェアハウスとの違い

◆賃貸住宅の変遷
賃貸住宅のスタイルとして(勝手な感覚として)長屋(江戸時代)▶下宿・間借り(明治・大正)▶アパート・マンション(昭和・平成)▶シェアハウス(平成・令和)といった変遷を経てきたんじゃないかなと思っています。
長屋は落語の世界で出てくるような四畳半+土間1.5畳のようなもので、台所は各部屋にありますが、水道(井戸)とトイレ(厠)は共同。風呂は銭湯です。
下宿・間借りは学校制度ができ、都市部で単身で生活する需要が生まれたため、増えてきた賃貸住宅のスタイル(・・・と思っています)。夏目漱石の「三四郎」とか「こころ」とか「坊ちゃん」、太宰治の「人間失格」あたりのイメージです。
部屋だけが各個人のスペースで、台所・トイレは共同。風呂は銭湯というのが一般的だったと思われます。
そして、プライバシー意識の高まりとともに、アパート・マンションなどに学生たちは住むスタイルになり、再度、共同生活というスタイルの利点(リーズナブル・コミュニティ)が見直され、シェアハウスという流れになってきました。
そう。
下宿とシェアハウスはその生活スタイルが似ているので混同されがちですが、アパート・マンションが一人暮らしの一般的な生活拠点となる「前」か「後」に出現したかに大きな違いがあります。
◆間口の広さはアパート・マンションなみ。生活スタイルの違いとしての下宿。
下宿→アパート・マンションにおいては昭和中期~平成中期くらいまでに緩やかに世代交代が行われたため、シェアハウスなどの生活スタイル・契約スタイルと違い、家賃の違いや共有部分の有り無しは明確ですが、契約などの書類の手間が大きく違うかといったらそういうわけではありません。
一方、アパート・マンション→シェアハウスの過程では、一種の革命みたいなもんですから、アパート・マンションのマイナス面を一気に無くそう!という急激な変化が見られます。
そのため、契約スタイルが一気に簡便化されていたり、「寝泊りさえ出来ればいい」といった2畳間などの部屋というかブースみたいなものもシェアハウスとして提供されています。
下宿とシェアハウスはここに大きな違いがあるような気がしています。
下宿はシェアハウスと違って決して「誰でも気軽に入れる」わけではありません。
下宿時代からアパマン時代にゆるやかに変遷したように、これらは地続きですからアパート・マンションが不動産屋の審査があるように、下宿にも(不動産屋を介していなかったとしても)大家さんなどに「うちに合うかどうか」一種の審査を受けることになります。
そのため、下宿の方がシェアハウスよりも入居のハードルは高くなるような気がしていますが、入居した場合はしっかりと管理がされているため、安心して長く住めるんじゃないかと思っています。
◆下宿は飽きがこない普遍的な生活を提供したい。
実態調査のシェアハウス入居目的にもあったように「コンセプトが気に入ったから」を挙げている方がいますが、シェアハウスにおいて、「ただ安く住めるだけ」タイプではなく生活に付加価値を加えたシェアハウスにはコンセプトがあったりします。
「バイク好きが集まる」とか「毎週金曜日はパーティ開催」とか「契約農園の米は食べ放題」とか「家具はすべて民芸家具」とかそういったやつです。
一方、下宿はあくまで暮らす場、「ふつうの暮らし」をする場ですから、明確なコンセプトがあるわけではありません。安心して暮らせる場を提供することが一番重要なことで、住民同士の交流などは自然発生的に、「促す」程度に、スパイス的に提供出来たらみんな円満に暮らせるのではないかと考えているフシがあります。
そのため、シェアハウスと比べると大きな付加価値があるかといえばあまりないんじゃないかと思っています。下宿は。
どちらかといったら、キャッチ―なコンセプトよりも、普遍的な「ふつうの暮らし」を丁寧に提供するということに重点が置かれているような気がします。
その中に「たまたま」アパート・マンションと違って共有空間がある「だけ」な考え方です。
◆「ツナギ」でなく安心して住み続ける共同生活のスタイルとして。
これらのことから、実態調査の「当初から短期的に居住するつもりだったから」シェアハウスに入居する場合とは違い、「ふつうに暮らす」選択肢の一つとして、アパート・マンションを選ぶ延長線上として下宿があり、独立してシェアハウスがあるような図式が見て取れます。
アパート・マンション・下宿が地続きで、それと一線を画した生活スタイルであるシェアハウス。
設備としては下宿とシェアハウスは共通項が多くなりますが、ソフト面で考えると「ふつうに安心して暮らす>毎日楽しく暮らす」である下宿と「ふつうに安心して暮らせる<毎日楽しく暮らす」シェアハウスという違いがあるんじゃないかと考えました。
◎「浅間温泉下宿 篶竹荘」と「下宿 第2ペンギン荘」
◎↓↓↓カタい話じゃなくて長野や松本での「暮らし」をのぞいてみたい方は↓↓↓
◆松本・浅間温泉での「ふつうの暮らし」「日常」を見てみたい。
「篶竹荘」や「第2ペンギン荘」でもブログやったり、InstagramやFacebookをやったりしています。
同じような人が書いているので、隠しきれない個性はそのままに、信州・松本・浅間温泉での「ふつうの暮らし」とか「日常」をメインテーマとして書いています。
併せて読んでいただけると、より長野県や松本でへの移住、そして暮らしが立体的に知っていただけると思います。
(と、言いますかSumSumの「お知らせ・読みもの」だけが異質です。よくたどり着いてくれました。ありがとうございます。)
▶合同会社SumSum「おしらせ・読み物」
→もっともカタい文章を書いています。
→「こうやったらもっと暮らしって楽しくなりそうだなー」みたいなことを書いています。
→「ふつうの暮らし」「日常」をちょっと楽しくする提案やデータなどをもとにした考察みたいなのも。
→自分にとっての「快適な暮らし」を求めている人にとって何かのきっかけになれば。
→「会社のサイト」だから一番真面目に書かなきゃ・・・と思って「他よりは」根拠になる資料を探しているつもりです。
▶篶竹荘「ブログ」
→「ぽん」のInstagramをもとに短い文章で書ききれなかった情報を加えて「より詳しい」日常、ふだんの暮らしを投稿します。
→ブログの中ではもっとも「素」です。
▶第2ペンギン荘「お知らせ・ブログ」
→第2ペンギン荘のマスコット「第2ペンギン」がいろいろやってみる「てい」で書いています。
→一番DIYについて書いているかもしれません。
→ちょっとおふざけしています。
→一番楽しんで書いているかもしれません。
→第2ペンギンはこんなやつです→(調子に乗ってラインスタンプも作りました。)
▶Instagram「第2ペンギン荘」
→第2ペンギン荘のInstagramです。
→女子目線の信州・松本・浅間温泉の移住暮らし。
▶Instagram「ぽん(篶竹荘と第2ペンギン荘)」
→篶竹荘と第2ペンギン荘のInstagramです。
→篶竹荘に住んでいるので篶竹荘の投稿が多め。
→個人的な趣味を投稿するあまり「大外れ」することも。